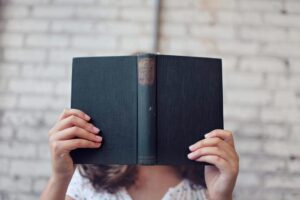Bloomのタキソノミー
Bloomのタキソノミー
・Bloomの目標分類学(Taxonomy)は教育学の分野で知られる理論の一つで、1956年に刊行された。
・教育者はこの分類法を用いて学習成果(learning outcomes)を設定し、単に学習する内容だけでなく、学習者にどの深度まで達してほしいかを明確化させる。
・さらに、その成果に対応した評価法をデザインし、学習者の達成度をなるべく正確に測定する。
・ブルームのタキソノミーは大きく3つのドメインから構成される。
- 認知領域/cognitive domain (Knowledge)
- 情意領域/affective domain (Skill)
- 精神運動領域/psychomotor domain (Attitude)
・各領域には学習のレベルが階層的に設定されており、あるレベルで求められる思考や技能は、それより低いレベルの内容を包含する。
・たとえば、認知領域において「分析(analysis)」ができる学習者は、その前段階として「知識(knowledge)」や「理解(comprehension)」を獲得し、「適用(application)」の方法を知っていることが前提とされる。
・2001年にはBloomの共同研究者の一人であるDavid KrathwohlとLorin Andersonらによって、認知領域の改訂版が発表された。
・この改訂では、従来の名詞的表現から動詞的表現へと用語を一新し(例:「記憶する」→「remember」など)、学習の成果を「獲得(acquisition)」から「能動的な遂行(active performance)」へと焦点を移した。また、従来の最上位にあった「統合(synthesis)」を「創造(create)」に置き換え、最上位レベルとして位置づけている。
認知領域
<1.0: understand(記憶(知識))>
・学習成果例:登場人物の名前や関係性を記憶する。
・評価方法例:複数選択式テストを実施し、学習者が資料を効果的に暗記できているかを確認する。
・根拠:複数選択式テストは、学習者の記憶状態を測定するのに適している。
<2.0: understand(理解)>
・学習成果例:劇や文学作品の主要なアイデアを理解し説明する。
・評価方法例:プロットと重要な出来事を1ページで要約する短いレポートを作成する。
・根拠:要約作成により、学習者が主要アイデアを把握しているかを評価できる。
<3.0: apply(適用)>
・学習成果例:作品の主要なテーマを別の文脈に適用する。
・評価方法例:登場人物のひとりに対するアドバイスコラムを執筆する。
・根拠:別文脈での応用を通じ、学習者が概念を理解し活用できているかを評価する。
<4.0: analyze(分析)>
・学習成果例:各登場人物の役割と相互関係を分析できる。
・評価方法例:主人公と対立者を比較する分析レポートを作成する。
・根拠:分析課題を通じ、学習者の批判的思考と理解の深さを測定する。
<5.0: evaluate(評価)>
・学習成果例:登場人物の意思決定を評価し、テキストの証拠をもとに支持または批判する。
・評価方法例:出来事に対する応答文を執筆し、テキストの根拠と個人的見解を論理的に組み合わせる。
・根拠:判断と論証を要求することで、高次思考を促す。
<6.0: create(創造)>
・学習成果例:類似のプロット要素を用いて新しい創作文章を作成する。
・評価方法例:異なる時代や設定で短編小説を執筆する。
・根拠:既存の知識を統合し、新規に構築する能力を示す。
情意領域
<1.0: receiving(受容)>
・学習成果例:他者の発表を尊重して傾聴する。
・評価方法例:他学生のプレゼンテーションに参加し、その要点をまとめる。
・根拠:受容段階での傾聴行動を通じ、価値観の認識を促す。
<2.0: responding(反応)>
・学習成果例:聴衆の前で効果的に話し、質問に応答する。
・評価方法例:クラスで発表を行い、質疑応答を実施する。
・根拠:積極的な参加と応答を通じて、情意的な関与を評価する。
<3.0: valuing(価値づけ)>
・学習成果例:自らの価値観を明示し、説明できる。
・評価方法例:あるトピックについて意見文を書き、自身の立場と根拠を示す。
・根拠:価値の形成とその理由を探求する。
<4.0: organization(組織化)>
・学習成果例:異なる価値システムを比較し、それぞれの証拠を評価する
・評価方法例:文化的価値体系を整理・比較し、その違いの背景を考察する。
・根拠:価値体系の構造的理解を深める。
<5.0: characterization(個性化)>
・学習成果例:チームで協働し、良好なチームワークを発揮する。
・評価方法例:グループプロジェクトに参加し、役割分担と協働を実践する。
・根拠:価値観の内在化と行動への影響を評価する。
精神運動領域
<1.0: reflex(反射)>
・学習成果例:物理的刺激に本能的に反応する。
・評価方法例:ドッジボールのゲームを行い、反射動作を観察する。
・根拠:即時反応能力を測定する。
<2.0: basic fundamental movements(基本的動作)>
・学習成果例:走る、投げるなどの単純動作を実行する。
・評価方法例:ドッジボールのゲームで動作を観察する。
・根拠:基礎的運動技能の習得度を示す。
<3.0: perceptual abilities(知覚能力)>
・学習成果例:複数の感覚を統合して動作を行う。
・評価方法例:キャッチボールやサッカーなどで視覚と運動を組み合わせる。
・根拠:感覚統合能力を評価する。
<4.0: physical abilities(身体能力)>
・学習成果例:一定時間持続的に活動を行う。
・評価方法例:25分間の持続的ランニングを行う。
・根拠:耐久性と体力を測定する
<5.0: skilled movements(熟練運動)>
・学習成果例:目標達成のために動作を適応させる。
・評価方法例:サッカーや戦略的ゲームで動きを最適化する。
・根拠:動作の適応性と戦略的思考を示す。
<6.0: non-discursive communication(非言語的コミュニケーション)>
・学習成果例:意図的な動作を通じて自己表現を行う。
・評価方法例:チームスポーツなどで動きを通して意思伝達を行う。
・根拠:身体的表現と協調性を評価する。
<参考ページ>
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/catalogs/tip-sheets/blooms-taxonomy