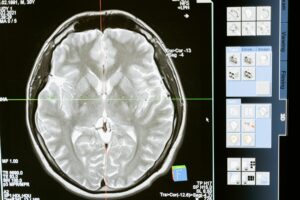発熱性好中球減少症 2024年AHIHOガイドライン
以下はドイツ血液腫瘍学会(DGHO)の感染症ワーキング部門(AHIHO)により提供された、2017年ガイドラインの更新版を参照に記載。
疫学
・発熱性好中球減少症の発症時に経験的な抗菌薬治療を迅速に開始することは重要だが、可能であれば治療を標的化するために十分な診断的評価も必要である。
・ただし、CNSやその他の皮膚常在菌(例:Corynebacterium、Bacillus属、Micrococcus属、Cutibacterium acnes)が1セットのみの血液培養で検出された場合、それはコンタミネーションの可能性があり、それをもとに必ずしも抗菌薬の変更を行うべきではない。
・さらに、がん患者におけるウイルス感染や真菌感染もFUOの原因となりうるが、それらは高い死亡率を伴う可能性がある。
・真菌感染については、抗菌薬治療中の72〜96時間を経ても症状が持続する場合には、特に鑑別すべきであり、疑われる場合には早期に治療を開始することが望ましい。
・最適な診断的評価を行っても、約半数の患者では原因微生物や疾患が同定されないため、抗感染治療は経験的治療のままとなることが多い。このため、地域の疫学に基づいた適切な経験的治療の選択が極めて重要となる。
・近年、FNを呈する血液腫瘍患者における菌血症の原因菌として、以前と異なり、現在はグラム陽性菌とグラム陰性菌の比率が拮抗していることが報告されている。
・米国で行われた多施設研究「BISHOP試験」でも同様の結果が得られており、血液悪性腫瘍をもつFN患者343例(FUO患者)から得られた389の病原体のうち、グラム陽性菌とグラム陰性菌の比率は同程度だった。このうち290件は単一の好気性菌による感染であり、12%は多菌種感染だった。グラム陰性菌では、Escherichia coli(22%)、Klebsiella属(9%)、Pseudomonas aeruginosa(7%)が多く、グラム陽性菌ではStreptococcus viridans群(24%)、Staphylococcus aureus(8%)、Enterococcus属(4%)が報告された。
診断評価
・抗菌薬の迅速な開始は重要であるが、同時並行で感染源の推定も行う必要がある。
・身体診察は、肺、皮膚および粘膜(特に肛門周囲、穿刺部位、CVC出口部、鼻腔周囲、副鼻腔)および局所感染症の症状(呼吸器、消化器、泌尿器、中枢神経系)に重点を置いて行う。
・ペニシリンやβラクタム系抗菌薬に対するアレルギーを自己申告する患者では、PEN-FASTスコアに基づいてリスクを再評価し、低リスクと判定された患者にはさらなる検査なくペニシリン治療が可能なことがある。スコア0点の患者では安全にペニシリン治療を実施できる。スコアが2点未満の患者では、前処置なくアモキシシリン250mgの経口負荷試験を安全に行える。ただ、実際に実施されることは少ないと思われる。
・FNの患者では、迅速かつ徹底した評価が必要であり、身体所見、検査、必要に応じた画像診断を行う。ただし、抗菌薬投与の開始は遅らせてはならない。
・評価の目的は、非感染性の発熱原因の除外、感染病巣や病原体の同定、炎症の重症度の評価であり、治療方針の決定に寄与する。
・呼吸不全、意識障害、血圧低下がある場合には、速やかにICUへの入室を検討する。
・身体所見は初診時に注意深く行い、入院中は少なくとも1日1回以上繰り返して評価し、病原体の同定と治療指針に役立てる。
・抗菌薬投与前には必ず血液培養を行うべきであり、原則異なる部位から2セット提出する。また、CVCが留置されている場合には、CVCからの追加採取も有効である。
・CVCがマルチルーメンである場合は、それぞれのルーメンから培養を採取することで診断精度が上がる。なお、治療開始後の定期的なフォローアップ血液培養は、診断的意義が少ないため推奨されない。
・ただし、以下の場合にはフォローアップ血液培養を行うべきである:
- S. aureusやCandida属の検出があった場合
- 新たな発熱、臨床状態の悪化があった場合
- 臨床的に治療反応が不十分で抗菌薬耐性が疑われる場合
・プロカルシトニン(PCT)の測定は菌血症の可能性評価に有用である。
・Multiplex PCRは、診断時間の短縮と精度の向上に役立つが、多菌種感染では特異度が低下する可能性がある。これらの検査は感受性情報を提供せず、死亡率の低下に寄与するエビデンスも現時点ではないため、血液培養などの標準的な検査を代替するものではない。
画像検査
・症状に応じた画像検査が推奨される。
・呼吸器症状がある場合は胸部CT、腹部感染が疑われる場合には腹部CTを行うことが検討される。
・一方で、好中球減少状態では浸潤影が認められにくく、胸部X線の感度が低いため、使用は推奨されない。肺炎の存在を疑えば、原則胸部CT撮像が望ましい。
・発熱が持続する患者では、PET-CTにより感染源の除外や抗菌薬のde escalationが可能であると報告されており、PIPPIN試験でその有用性が示されている。
侵襲性真菌感染症のスクリーニング
・好中球減少が7日を超えると予想される高リスク患者では、侵襲性アスペルギルス症(Invasive Aspergillosis: IA)を早期に検出するため、週2回程度の頻度でガラクトマンナン(Galactomannan: GM)抗原を測定することが推奨される。
・気管支鏡検査およびBAL(気管支肺胞洗浄)を行う場合は、全例でBAL液からのGM測定を実施すべきである。
・代替の手段として、血清β-D-グルカンの測定も提案されている。ただし、この成分はカンジダ症(Candidiasis)やニューモシスチス肺炎(Pneumocystis pneumonia)など、さまざまな病原真菌の細胞壁に含まれるため、特異性という観点で制限がある。
・いずれにしても、血清ガラクトマンナン抗原あるいはβ-D-グルカンの測定は、IAの診断において臨床所見、内視鏡検査、培養による微生物学的検査を代替するものではない。
リスクの層別化
・好中球減少は死亡率の上昇と関連しており、このことは固形腫瘍を有する患者にも当てはまる。
・発熱性好中球減少症(FN)は初回の治療サイクル中に発生しやすいため、リスク予測を目的としたFENCEスコア(Febrile Neutropenia after Chemotherapy score)を治療前に用いることで、G-CSF製剤や予防的抗菌薬の使用、モニタリングの最適化に役立つことがある。
・CRP、PCTなどの炎症マーカーは、FNの重症化リスクの予測に広く用いられている。なかでもPCTは、菌血症の予測精度においてCRPよりも高いことが示されている.
・PCT陽性は、集中治療室(ICU)への入室および死亡の予測因子であることが、後ろ向きコホート研究により示されている。
・MASCCスコア(Multinational Association for Supportive Care in Cancer score)は、外来患者のリスクを層別化する目的で開発された。入院患者においても適用可能であり、スコア21点未満の患者は高リスクとされ、菌血症、ICU入室、死亡といった転帰と関連している。なお、MASCCスコアにPCTを加えることで、菌血症や死亡を含む重篤な合併症のリスクがより正確に予測できるとされている。
・qSOFAスコア(quick Sequential Organ Failure Assessment)は、FN患者における敗血症やICU入室、死亡のスクリーニングには不適切であり、MASCCスコアと比較して感度・特異度が劣るとされる。
・CISNEスコア(Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia)は、一見安定して見えるFN患者の中から、実際には重篤な合併症をきたしやすい患者を識別する目的で開発された。救急外来に搬送された低リスク患者の識別において、MASCCスコアよりも有用であるとされている。
初期治療
<リスクに基づく初期治療戦略>
・FNにおける初期対応は好中球減少の予測期間および臨床的リスク因子に基づいて分類される。
・好中球減少が7日を超えると予想される患者は「高リスク」とされ、FNの複雑な経過をたどる可能性が高い。
・一方、好中球減少が7日以内と予想され、かつ追加の臨床的リスク因子がない場合は「標準リスク」とされる。
・標準リスクであってもリスク因子が追加で存在する場合(例:心不全、腎不全、初回化学療法など)は「高リスク」として扱う。
・臨床的なリスク因子がない標準リスク患者では、外来管理が可能な場合がある。
<高リスク患者に対する初期抗菌薬治療>
・好中球減少が7日を超えるか、7日以内であっても臨床的リスク因子を有する高リスク患者に対しては、以下の点に注意する。
・FN発症後、できるだけ早期に抗菌薬治療を開始すべきであり、カバーすべき細菌としては、腸内細菌科細菌(Enterobacteriaceae)、緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)、レンサ球菌(Streptococcus属)である。
・多剤耐性菌(MDR:MRSA、VRE、ESBL産生E. coli)による定着が確認されている場合であっても、現時点では併用療法の有用性を支持するエビデンスは乏しい。
・ただし、敗血症性ショックや重症感染の際には、MDR菌による菌血症のリスクが高いと考えられる場合に限り、併用療法を考慮してもよい。
・微生物学的検査結果に基づき、適切にDe escalationを行う。
・経験的治療(empiric therapy)に推奨される第一選択薬としては、PIPC/TAZ、IPM、MEPM、CFPMが挙げられる。
・VCM、TEIC、LZDの経験的追加投与も、有効性を示すエビデンスは存在しない。
・皮膚軟部組織感染症(SSTI)、CRBSI,肺炎を疑う状況や全身状態が不良な状況では、MRSAをカバーする目的でVCMの投与を検討する。ただし、全例でのルーチンのカバーは必要ない。
・肛門周囲膿瘍や好中球減少性腸炎を疑う場合は嫌気性菌カバーが望ましい。
<抗菌薬の投与時間に関する考察>
・FN患者105例を対象としたRCTでは、PIPC/TAZまたはCAZの延長投与(4時間)により、標準投与(30分)よりも複合アウトカム(解熱、血液培養の陰性化、症状改善、治療変更不要)の達成率が有意に高かった。
・一方で、別のRCT(n=63)では、CFPMの延長投与と標準投与の間で72時間後の解熱率に有意差はなかった。
・後ろ向き研究では、CFPMの延長投与の方が標準投与に比べて解熱までの時間が短縮される傾向が示された。
・よって、FN患者においては、βラクタム系抗菌薬およびCFPMの延長投与を検討してもよい。
外来治療が選択可能なケースの初期治療
・MASCCスコアが高く(>21点)、以下に示す臨床的条件をすべて満たす患者では、裕二に迅速な受診ができたり、見守りがなされている環境にあったりするようなケースでは外来管理および経口治療が可能である。ただ、実際には外来治療となるケースは少ないと予想される。
・外来および経口治療が可能な標準リスク患者にはAMPC/CVA、LVFXの併用療法が選択肢に挙げられる。
・治療中は日々の臨床的モニタリングが必須である。臨床的不安定性、解熱の遷延、治療への非遵守が見られた場合には、即座に入院対応へ切り替える必要がある。
抗菌薬終了の判断
・臨床的に感染源が診断されている場合は、好中球数 500/μL以上、かつ特定された感染巣に対して十分な治療期間がなされるまで治療を行うこととなる。
・感染源が不明なままの場合は解熱して2日間以上経過、かつ好中球数が500/μL以上になるまで治療を行うこととなる。しかし、近年では好中球回復を待たずに治療を中止しても安全である可能性を示唆する報告が増えつつあり、今後の知見集積が待たれる。
2nd lineの抗菌薬治療
・FNにおいて解熱までの中央値は3〜5日とされている。
・初期の経験的抗菌薬治療から96時間以上が経過しても発熱が持続する場合、特に以下の条件を満たす場合には治療の変更を検討すべきである:
- 臨床状態の悪化
- 新たな発熱の出現
- 初期治療への治療反応性不良
・侵襲性真菌感染症(Invasive Fungal Infection: IFI)の高リスク患者において、発熱が持続し、抗菌薬に反応しない場合には、抗真菌治療の開始を検討する。
・経験的治療においては、キャンディン系薬(特にCPFG)は死亡率低下において最も効果的であり、MCFGは解熱効果において最も優れていたとされる。詳細は割愛するが、カンジダ菌血症を疑う場合はMCFG、侵襲性肺アスペルギルス症を疑う場合はVRCZ(あるいはAMPH-B)を検討する。
G−CSF製剤
・Rahul MhaskarらによるCochraneレビュー(2014年)では、抗生物質単独と比較してG-CSF製剤(G-CSFまたはGM-CSF)+抗生物質の併用療法を評価した14件のRCT(合計1,553例)をメタ解析された。
・結果として、全死亡率に有意な改善は認められなかった(ハザード比(HR) 0.74、95%CI 0.47–1.16、P=0.19)
・ただし、好中球(neutrophil)回復の加速、発熱持続期間の短縮、入院日数の短縮、抗生物質使用期間の短縮が示された。
・骨・関節痛やインフル様症状の増加が報告されている。
・IDSA(Infectious Diseases Society of America)ガイドライン(2010年改訂版)では、発熱性好中球減少症の初期治療としては「抗生物質療法が最優先」としていて、G-CSF製剤はルーチンでの使用を推奨せず、深刻な合併症リスク(臓器障害、肺炎、菌血症、敗血症様症状など)がある高リスク患者に限定して考慮するよう勧められている。
・また、コストが高く、全例に投与すると資源の非効率的使用につながるため、ガイドラインに沿った適正使用が重要。
・がん化学療法による好中球減少症に対しては、フィルグラスチム(グラン®(バイオシミラー製剤も存在))、レノグラスチム(ノイトロジン®)が保険適応を有している。なお、持続型G-CSF製剤に相当するペグフィルグラスチム(ジーラスタ皮下注®)は、がん化学療法によるFNの"発症抑制"に関して保険適応を有し、発症したケースに関しては保険適応を有さない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
<参考文献>
・Sandherr M, Stemler J, Schalk E, Hattenhauer T, Hentrich M, Hertenstein B, Hohmann C, Mellinghoff SC, Mispelbaum R, Rieger C, Schmidt-Hieber M, Sprute R, Weiss G, Cornely OA, Henze L, Lass-Floerl C, Beutel G, Classen AY, Freise NF, Karthaus M, Koehler P, Krause R, Neuhann J, Orth HM, Penack O, Schaich M, Spiekermann K, Voigt S, Weissinger F, Busch E. 2024 update of the AGIHO guideline on diagnosis and empirical treatment of fever of unknown origin (FUO) in adult neutropenic patients with solid tumours and hematological malignancies. Lancet Reg Health Eur. 2025 Jan 31;51:101214. doi: 10.1016/j.lanepe.2025.101214. PMID: 39973942; PMCID: PMC11836497.
・Mhaskar R, Clark OA, Lyman G, Engel Ayer Botrel T, Morganti Paladini L, Djulbegovic B. Colony-stimulating factors for chemotherapy-induced febrile neutropenia. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 30;2014(10):CD003039. doi: 10.1002/14651858.CD003039.pub2. PMID: 25356786; PMCID: PMC7141179.