感染性腸炎 infectious enteritis
目次
Key recommendations for practice
- 急性下痢の患者において血便がみられるケース、重度の脱水が想定されるケース、炎症性病態(侵襲性下痢)を想定するケース、3~7日間以上症状が続くケース、免疫抑制患者で便培養の提出を行う(Evidence rate: C)
- 入院3日後以降に下痢が生じた患者ではCDトキシンA/Bの検査を実施するべきである(Evidence rate: C)
- 急性下痢の第一の治療は水分補充であり、可能であれば経口補水を優先する(Evidence rate: C)
- ロペラミドおよびジメチコンの併用は急性下痢をどちらかによる単剤治療よりも迅速かつ完全に改善させる可能性がある(Evidence rate: B)
- 抗菌薬は渡航関連下痢症の有症状期間と重症度を軽減する(Evidence rate: A)
鑑別診断
・急性下痢の原因となる感染症としてはウイルス性、細菌性、そして稀ながら寄生虫によるものが挙げられる。非感染性疾患としては消化器疾患、薬剤の副作用、内分泌疾患(甲状腺機能亢進症など)などが挙げられる。
・臨床的に、急性の感染性下痢症は非炎症性(ほとんどがウイルス性で比較的軽症)と炎症性(ほとんどが侵襲性あるいは毒度産生性で比較的重症)とに大別される。
・急性下痢症の最も一般的な原因はウイルス性である。細菌感染は海外旅行、食中毒と関連することが多い。
非炎症性下痢症の特徴
・悪心/嘔吐、疝痛様の腹痛、非血便、水様便を特徴とし、発熱は伴わないことが典型。
・便中白血球はみられにくい。
・原因微生物としては腸管毒素原性大腸菌(ETEC)、C.perfringens、B.cereus、S.aureus、ロタウイルス、ノロウイルス、ジアルジア、クリプトスポリジウム、ビブリオ(V.cholerae)が挙げられる。
・比較的軽症である。
炎症性下痢症の特徴
・腹痛、テネスムス、血便を特徴とし、発熱を伴うことが典型。
・便中白血球がみられやすい。
・原因微生物としてはサルモネラ菌(非チフス性)、赤痢菌、キャンピロバクター、腸管出血性大腸菌(EHEC)、C.difficille、Entamoeba histolytica、エルシニア菌が挙げられる。
・比較的重症である。
病歴聴取/リスク因子の同定
・下痢の出現時期、持続期間、頻度などを把握し、便性状(水様便、血便、脂肪便など)に注意して聴取を行う。
・尿量減少、口渇、意識障害などをはじめとした脱水徴候の有無について評価する。
・嘔吐はウイルス性疾患、あるいは毒素産生性細菌の関与を疑う。
・喫食歴や旅行歴は特定の原因微生物を想定することに役立つ場合がある。
・またSick contactの有無、直近での抗菌薬使用歴にも注意する。
・ほか、腹部手術歴、骨盤内放射線照射歴、免疫抑制の有無(AIDs、ステロイド長期使用、化学療法など)も把握する。
原因微生物ごとの臨床的特徴
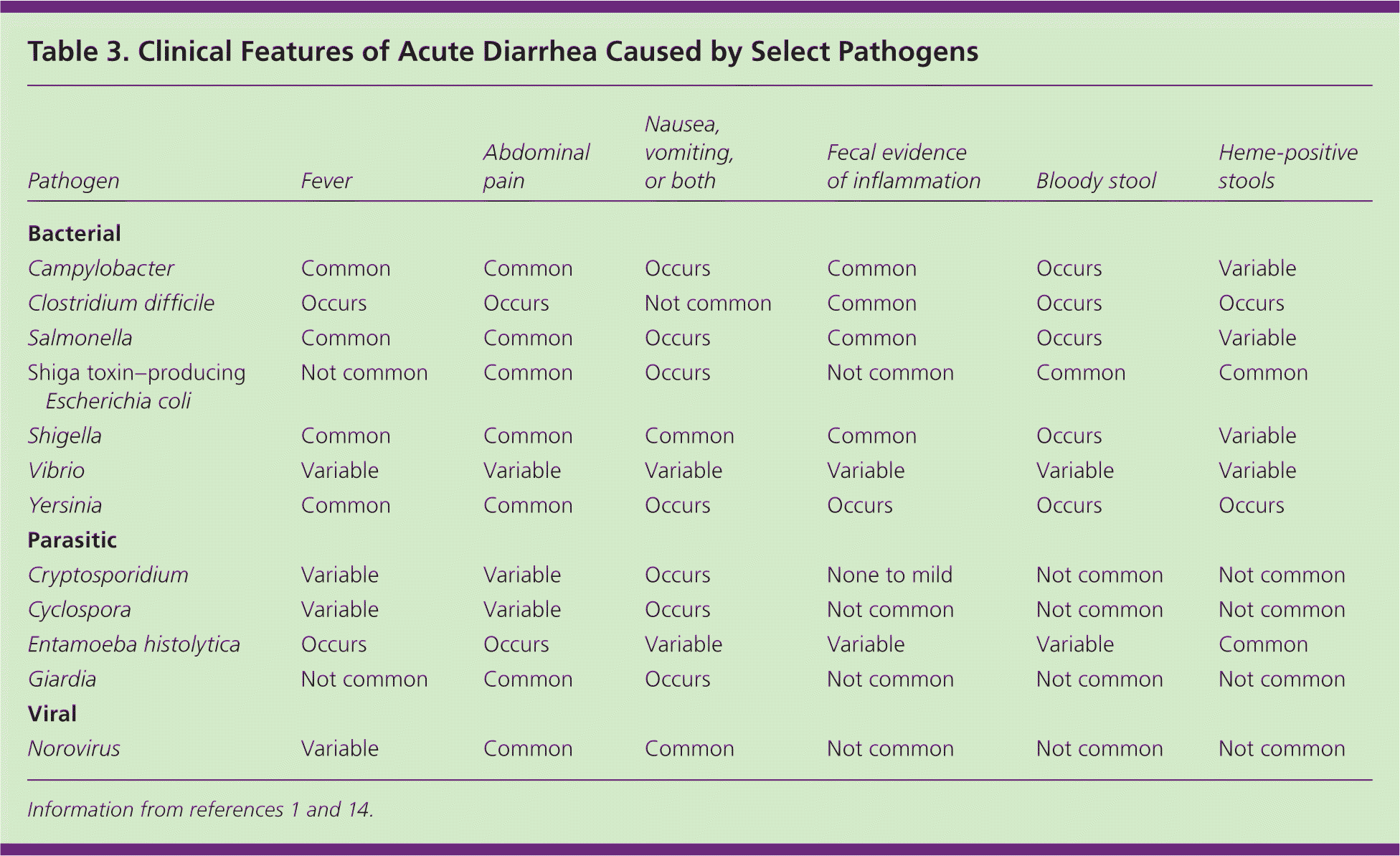
身体診察
・身体診察でまず重要な点は患者の脱水の程度を評価することである。
・一般的にはGeneral appearance、頬粘膜や腋窩の乾燥所見、CRT延長、頻脈、起立時のバイタルサインの変動などで推定が可能。
・発熱がみられる場合は非炎症性下痢症よりも炎症性下痢症を優先的に考える。
・腹部診察では他の鑑別疾患の可能性を想定して行うことが重要。また直腸診では血液成分の評価、便の硬さなどを評価できる。
臨床検査
・水様便が主症状の場合の多くではSelf-limitedな経過を辿るため、通常、精査対象とはならない。
・一般に臨床検査は重度の脱水が想定されるケース、重症感のあるケース、持続する発熱、血便がみられるケース、免疫抑制状態にあるケース、院内感染や集団感染が疑われるケースで行う。
・便中に白血球やラクトフェリンがみられる場合は炎症性下痢症を考える。ただ、現実的にこの検査を行って臨床判断を下すことは多くないと思われる。
・なお、炎症性下痢症に関する便潜血検査の診断学特性は先進国においては感度71%、特異度79%とされている。
・急性下痢をきたす全てのケースで便培養を提出することは非合理的であり、実際、全体の僅か1.6~5.6%でしか培養検査が陽性とならないとされている。なお、血便があるケースのみに限定して便培養を行うと陽性率は30%以上に上昇する。通常、便培養検査は血便がみられるケース、重度の脱水が想定されるケース、炎症性病態(侵襲性下痢)を想定するケース、3~7日間以上症状が続くケース、免疫抑制患者のケースで行う。
・渡航関連下痢症でも便培養は検討されるが、経験的治療を行うこともときに有用である。
・入院後3日以降に下痢が生じた場合にはCDトキシンA/Bの実施が推奨される(通称、3 day rule)。通常は15~20%で陽性となることが知られている。C.difficille感染症(CD腸炎)を発症するリスクは抗菌薬投与中あるいは投与終了後の1ヶ月間で7~10倍に増加し、投与終了後の2~3ヶ月間であっても約3倍に増加する。したがって、抗菌薬投与後3ヶ月以内の下痢ではCDトキシンA/Bの実施は推奨される。そのほか、PPI投与などもC.difficille感染症のリスク因子となり得る。
内視鏡検査
・急性下痢において内視鏡検査の有用性は限定的である。
・原則として、便培養や血液検査などで原因が特定できず、経験的治療などが無効な場合で内視鏡検査を考慮することとなる。
・特に腸結核、炎症性腸疾患(IBD)、顕微鏡的腸炎(NSAIDsやPPI投与が原因となる)、悪性腫瘍に伴う下痢などを疑うケースでは内視鏡検査による観察と、生検検査が有用である。
水分補給
・急性下痢の第一の治療は水分補給であり、可能であれば経口補水が優先される。
・まずは脱水の程度を評価することが重要で、ときに平時の体重と受診時の体重との差を確認することも有用である。経口補水液(ORS)は有用である。
止痢薬
・ロペラミドは渡航関連下痢症で抗菌薬に併用して使用することで、下痢の期間を約1日短縮させることが示されている。また、ロペラミドおよびジメチコンの併用は急性下痢をどちらかによる単剤治療よりも迅速かつ完全に改善させる可能性がある。
・ロペラミドは炎症性下痢の患者においてはときに危険な疾患の罹病期間を延長させる可能性があるため、使用すべきではない。あくまで非炎症性下痢のケースに限定して使用するべきである。
・ビスマスは炎症性下痢のケースにおいて比較的安全に使用可能である。他にタンニン酸アルブミンも止痢薬として存在するが、牛乳由来の成分を含むため、牛乳アレルギーの方には使用しないことが無難である。
抗菌薬
・前述のとおり、急性下痢の多くはウイルス性によるSelf-limitedな病態であるため、通常、抗菌薬の使用は推奨されない。さらに抗菌薬の過剰使用により耐性菌を増加させたり、腸内細菌叢を乱したり、CD腸炎を発症させたりするリスクが上昇する。
・一方で、抗菌薬は赤痢菌、カンピロバクター腸炎、渡航関連下痢症、原虫感染症に有効である。特に渡航関連下痢症では抗菌薬の使用が重症度低下と2~3日間程度の罹病期間短縮とに関連している。
・患者の臨床症状から腸管出血性大腸菌(EHEC)の関与が想定される場合には抗菌薬使用によって、溶血性尿毒症症候群(HUS)発症のリスクが高まるため、特に抗菌薬の使用に注意を要する。
・10~14日以上続く下痢の場合、抗菌薬治療を行わない治療方針は奏功しない可能性も想定され、原虫感染症に関する精査と治療を考慮するべきである。
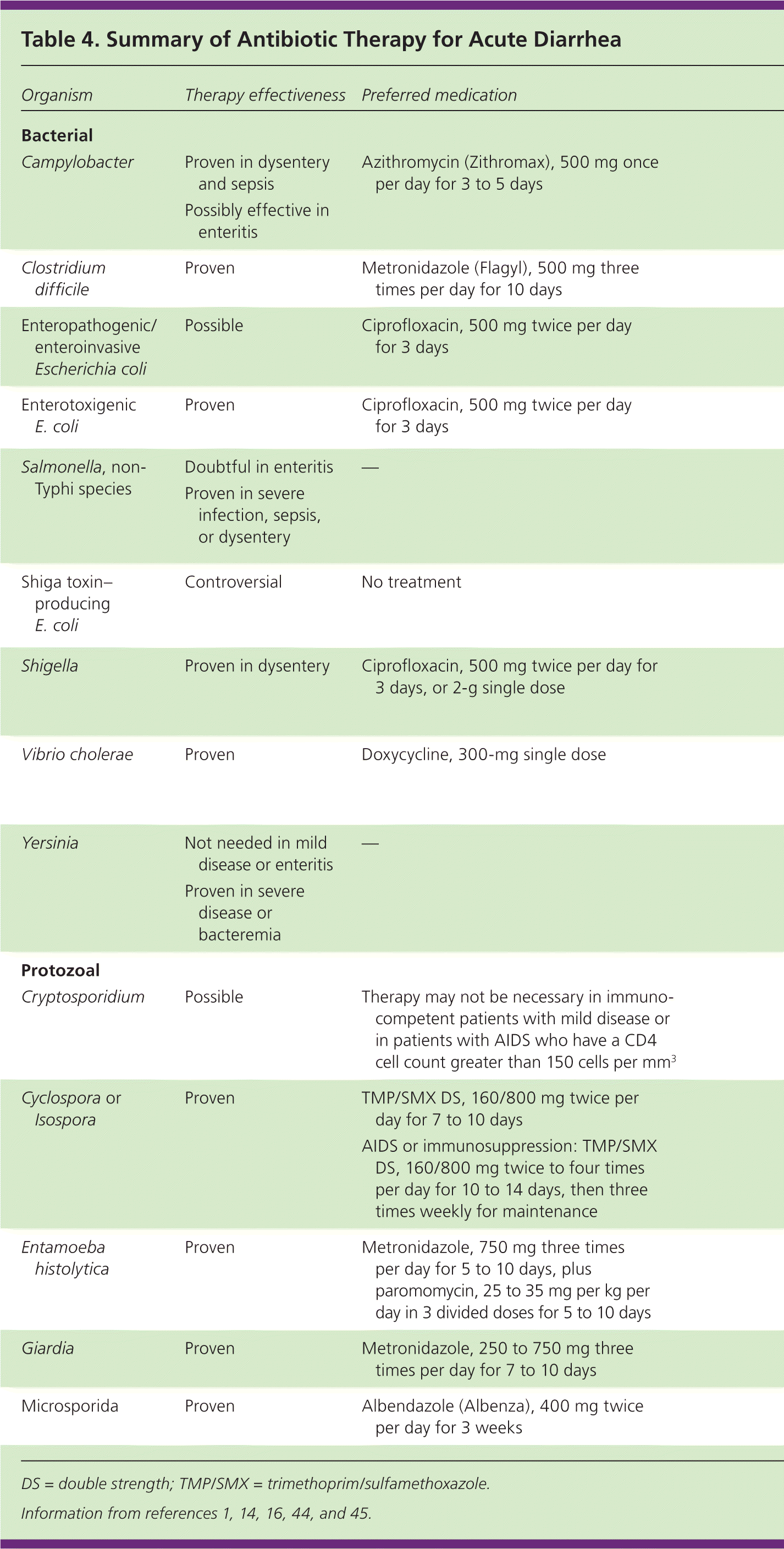
プロバイオティクス
・急性下痢の小児にプロバイオティクスを使用することで、重症度低下と1日間程度の罹病期間短縮とに関連することが示唆されている。
亜鉛補充
・小児を対象とした研究では特に発展途上国においては亜鉛補充(生後2ヶ月以上の小児に20mg/日 10日間)は急性下痢の治療と予防とにおいて重要な役割を果たしている可能性が示唆されている。
・ただし成人においてはエビデンスが十分でない。
発症予防
・衛生状態を良好に保つこと、手洗い、安全な食品管理、適切な上下水道整備などは下痢症を予防するうえで重要。
・手洗いを徹底する方策だけで下痢の発症率は約1/3に減少することが示唆されている。
・ワクチン開発は特に発展途上国の人々にとって有効である。これまでロタウイルス、腸チフス、コレラ菌に対して有効なワクチンが存在するが、カンピロバクター、腸管毒素原性大腸菌(ETEC)、赤痢菌に対するワクチンは研究中である。
―――――――――――――――――――――――――――――――
<参考文献>
・Barr W, Smith A. Acute diarrhea. Am Fam Physician. 2014 Feb 1;89(3):180-9. PMID: 24506120.

