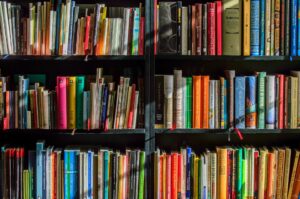Millerのピラミッド
Millerのピラミッド
・1990年に提唱された、Millerのピラミッドは医学教育の場面で学習者評価の際に利用される概念である。
・ピラミッドの各階層が学習者のスキルのレベルを指す。
・各階層はそれより下位の層を基盤として存在する。
・Millerのピラミッドは、教育プログラム設計や評価方法の選定において、知識から実践まで段階的にカバーする必要性を明示し、各層に応じた最適な評価手法を導入する指針を提供する。
各階層の内容
・最下層の“knows”は学習者が特定領域に関する知識をどれだけ保有しているかを評価し、いわゆるペーパー試験によって評価することが可能。
・次の“knows how”は知識を用いて臨床判断やマネジメントプランを立案する能力を評価し、症例問題や論述式問題で評価される。
・次の“shows how”はOSCEやシミュレーションといった模擬臨床環境での行動や手技を実演できるかを評価する。
・さらに上位の”does”は 実際の臨床現場における日常業務でのパフォーマンスを観察・評価し、現場での実践力を測定する。直接観察(direct observation of procedural skills)や360度評価、多面的フィードバックによって評価される。
・こちらのページの図が参考になる。