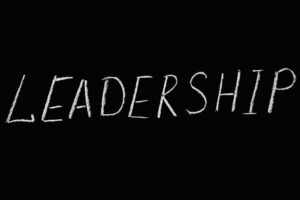複雑性悲嘆 complicated grief
死別と悲嘆
・死別(bereavement) とは、愛する人を死によって失う経験であり、人生における最もつらい出来事の一つである。
・それは身体的、心理的、社会的な影響を伴う。
・愛する人は、支えを提供し、個人のアイデンティティや帰属意識の形成に寄与する。
・悲嘆(grief)は死別に対する反応であり、多様な心理的・生理的症状を含み、時間の経過とともに変化する。その表現や経過は個別であるが、共通点も存在する。
急性悲嘆
・愛する人の死を知った後に始まる急性悲嘆(acute grief)の時期には、「分離反応(separation response)」とストレス反応の要素が存在する。
・強い切望、悲しみが特徴であり、死者のことを考えたり、死者のイメージが頻繁に浮かぶ。
・死者の声を聞いたり、姿を見たり、存在を感じたりすることがあり、これは幻覚の一種で通常は問題とならない。ここで幻覚を拡大解釈せずに、慎重に経過をみることも可能。
・自分のアイデンティティや社会的役割に混乱を感じ、通常の活動から離れ、死別を信じられずにいることもある。
・急性悲嘆の症状には、抑うつ、不安、怒りなどがあり、これらは心拍数や血圧の上昇、コルチゾールレベルの上昇、睡眠障害、免疫機能の変化などの生理的変化と関連する。
・死別後の初期の期間は、心筋梗塞やたこつぼ型心筋症(ストレス心筋症)などの健康リスクの上昇と関連する。また、気分障害、不安障害、物質使用障害の発症リスクも高まる。
喪失への適応(adaptation of loss)
・困難な喪失に適応する過程は長期にわたる場合があり、感情の波は予測できずに変動する。
・全体として、喪失やそれによる影響を理解し、将来の希望や計画を修正するにつれて、悲嘆の強さは次第に弱まる。
・しかし、命日や家族の行事、祝賀の場面では感情が再び高ぶることがある(記念日反応や命日反応とも呼ぶ)。
・ときに不適応な思考や行動、あるいは深刻な併存問題が悲嘆を複雑化させ、適応を遅らせたり、停止させたりする。
複雑性悲嘆
・複雑性悲嘆(prolonged grief disorder/complicated grief)は、世界人口の約2~3%に影響を及ぼす。
・これは常識的な期間を超えて長期間続き、日常機能を障害する強烈な悲嘆が特徴である。期間はイベントが生じてから6か月以上を目安とすることもあるようであるが、ケースごとに異なり、期間のみで一概に区別することは困難。
・親密な関係性を失った後に生じ、恋人や配偶者を亡くした場合は約10~20%、子どもを失った親ではさらに高頻度でみられる。
・突然死や衝撃的な死(自殺、他殺、事故)の後の発生率も高い。
・治療が行われない場合、症状は非常にゆっくりとしか改善せず、持続することが多い。
・睡眠障害、物質乱用、希死念慮や行動、免疫機能異常、心血管疾患やがんのリスク上昇とも関連する。
・睡眠障害は、複雑性悲嘆が健康に与える悪影響の一因と考えられる。
・さらに、複雑性悲嘆は、さまざまな疾患の治療計画の遵守を妨げる可能性がある。
・急性悲嘆と同様に、複雑性悲嘆の中心的な特徴は持続的で強烈な切望、渇望、悲しみであり、これは執拗な死者のイメージや思考、現実の受容困難と共に現れる。
・怒りや罪悪感を伴う反芻も多く、喪失を思い出させる状況を避けたり、死者の持ち物に執着する行動もみられる。
・孤立感、自己喪失感、社会的役割の変化に対する不快感があり、悲嘆が終わらないことに混乱する。
・家族や友人による助けがときに効かず、関係が悪化することで孤独感が深まることもある。
・複雑性悲嘆の原因は多因子的であり、気分障害や不安障害、物質乱用、複数回の喪失歴がリスク因子である。また、死別前の介護に伴う抑うつや、早期の悲嘆期における抑うつもリスクである。
・幼少期の困難な経験、死後の極端なストレス、社会的支援の不足、友人や家族との深刻な対立、経済的困難もリスクを高める。
アセスメントと診断
・複雑性悲嘆(complicated grief)に関する診断基準や正式名称については、現時点でコンセンサスが得られていない。
・DSM-5には「持続性複雑性死別障害(persistent complex bereavement disorder)」という名称で、一部の基準が盛り込まれ、さらなる研究が必要な疾患として位置づけられた。
・複雑性悲嘆を示唆する思考や行動の有無は、医療面接の場で評価される。
・強い悲嘆自体は病的とはいえないが、適応を妨げるような不適応的な思考や行動、過度に強く長期間持続する悲嘆は特に注意が必要である。
・患者は、自分の悲嘆がいつまでも強いことにときに恥ずかしさを感じている場合があるため、臨床家は、率直かつ共感的に直接質問することが重要である。
・また、「簡易悲嘆質問票(Brief Grief Questionnaire)」や「複雑性悲嘆インベントリー(Inventory of Complicated Grief)」といった自己記入式質問票もスクリーニングに使用できる。
・死別した人の臨床評価では、併存しやすい他の精神疾患や身体疾患のスクリーニングも行うべきである。
・複雑性悲嘆は、大うつ病(major depression)や心的外傷後ストレス障害(PTSD)と区別する必要がある。これまでのエビデンスによれば、複雑性悲嘆は、完全に独立した疾患というよりも、通常よりも重症で長期間続く急性悲嘆と捉えるのが妥当である。
・複雑性悲嘆では、喪失を思い出させるものを過度に回避したり、死の状況や結果に関する不適応な反芻を続けたり、社会文化的規範を超えて強く持続する急性悲嘆の症状が特徴である。
・ただし、悲嘆が「長期化しすぎている」と判断することは難しい。なぜなら、悲嘆に関する考え方は文化によって異なり、それを判断するための十分なデータがないからである。さらに、死別の状況によっても悲嘆の期間は異なる。たとえば、子どもを亡くした親の大多数が、18か月後のスクリーニングで複雑性悲嘆の陽性と判定されるという研究結果もある。
・現時点では、死別から6か月が経過した時点で複雑性悲嘆に対する治療を提案することが一般的な実践となっている。
自死リスクの評価
・複雑性悲嘆の患者における希死念慮の頻度は高い。
・しかし、この集団における実際の自殺既遂率に関するデータは乏しい。
・したがって、複雑性悲嘆の評価においては、必ず自殺企図や具体的な計画の有無を慎重に確認する必要がある。
・また、複雑性悲嘆の患者では、通常より危険な行動や健康問題の放置(運命に身を任せて死を招くような行動)が多く見られるため、それらについても具体的に質問する必要がある。
心理療法
・RCTで心理療法が複雑性悲嘆に有効であることが示されていて、第一選択の治療法とされている。なお、これまで幅広く研究されているのはCGT(Complicated grief treatment)という治療法である。
・この治療の目的は悲嘆を複雑化させている要因を特定し、解決すること、そして喪失への適応を促進することにある。治療は「再構築(restoration)」と「喪失(loss)」の2つの領域に重点を置く。
・再構築(restoration):効果的な日常機能を取り戻すために、意欲を高め、将来の計画を立てる。
・喪失(loss):死別に関する考え方を変え、怒り、罪悪感、不安といった強い感情を呼び起こさずに捉え直せるよう支援する。
薬物療法
・複雑性悲嘆に対する薬物療法に関して、ランダム化比較試験からのデータは存在しないが、実際の臨床では抗うつ薬がよく使用されている。
・50人の患者を対象とした複数のオープンラベル試験では、抗うつ薬投与により改善がみられたが、ベンゾジアゼピンでは効果が認められなかった。
――――――――――――――――――――――――――――――
<参考文献>
・Shear MK. Clinical practice. Complicated grief. N Engl J Med. 2015 Jan 8;372(2):153-60. doi: 10.1056/NEJMcp1315618. PMID: 25564898.